第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(注) 1.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は76,000,000株増加し、80,000,000株となっています。
2.2025年7月30日開催の臨時株主総会の決議により、発行可能株式総数は7,920,000株増加し、87,920,000株となっています。
② 【発行済株式】
(注) 1.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で1株につき20株の株式分割を行っています。これにより発行済株式総数は20,881,000株増加し、21,980,000株となっています。
2.2025年7月30日開催の臨時株主総会決議により、2025年7月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第5回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株です(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。)。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含みます。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとしています。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしています。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」と言います。)に「新株予約権の目的となる株式数」を乗じた金額としています。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとしています。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとしています。
さらに上記の他、当社が吸収合併新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認の議案もしくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
4.新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、本条において「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、甲又は甲の子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権の行使は、甲の普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
④ 上記③の定めにかかわらず、新株予約権者は、甲の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な甲の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(a) 甲の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b) 甲が他の会社と合併することにより、合併直前の甲の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c) 甲が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の甲の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d) 甲が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の甲の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e) 他の会社が甲株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の甲の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f) 甲が事業譲渡又は会社分割により甲の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
⑤ 本新株予約権の行使によって、甲の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)3に準じて決定する。
6.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員47名となっています。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株です。(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含みます。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとしています。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしています。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」と言います。)に「新株予約権の目的となる株式数」を乗じた金額としています。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとしています。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げるものとしています。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとしています。
さらに上記の他、当社が吸収合併新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、当該新株予約権者から新株予約権を無償で取得することが可能としています。
② 当社株主総会及び取締役会(取締役会を置いていない場合は、取締役の過半数の決定)において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割·新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することが可能としています。なお、「新株予約権の行使の条件」の規定により本新株予約権を行使することができる場合には、当該新株予約権の行使を妨げないものとします。
③ 当社は、本新株予約権者が本新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、取締役会(取締役会を置いていない場合は株主総会)が別途定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することが可能としています。
4.新株予約権行使の条件
① 本新株予約権の行使は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から6ヶ月が経過することを条件としています。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合はこの限りではありません。
② 上記①の定めにかかわらず、本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社の買収について、法令及び当社の定款その他の社内規則上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議または決定が行われた日以降別途当社が合理的に指定する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとしています。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味するものとしています。
(a) 当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す。
(b) 当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社または新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c) 当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d) 当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e) 他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f) 当社が事業譲渡または会社分割により当社の事業の全部または重要な一部を第三者に移転させること。
③ 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人または遺産による本新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合は当該発行済み新株予約権を行使できる場合があります。
④ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとしています。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは不可能としています。
⑥ 本新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」及び以下(a)から(d)において定める期間区分に従って、本新株予約権の一部または全部を行使することが可能としています。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数としています。
(a) 割当日から、割当日から起算して1年を経過する日までの間は、割当てられた本新株予約権を行使できないものとしています。
(b) 割当日から起算して1年経過した日から、割当日から起算して2年を経過する日までの間は、割当てられた本新株予約権個数のうち、3分の1までの本新株予約権を行使することができるものとする。
(c) 割当日から起算して2年経過した日から、割当日から起算して3年を経過する日までの間は、割当てられた本新株予約権個数のうち、3分の2までの本新株予約権を行使することができるものとする。
(d) 割当日から起算して3年経過した日以後は、割当てられた本新株予約権のすべてを行使することができるものとする。
⑦ 上記⑥の規定にかかわらず、当社の企業買収(上記に定義される)に関し、新株予約権者は、当該企業買収が完了した日以降、当該新株予約権が「新株予約権を行使することができる期間」に従い行使可能である限り、割り当てられたすべての新株予約権を行使できるものとしており、ただし、「新株予約権の行使の条件」②に基づく取扱いを受けるものとしています。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)3に準じて決定する。
6.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
第4回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株です。(ただし、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。)
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含みます。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとしています。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしています。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」と言います。)に「新株予約権の目的となる株式数」を乗じた金額としています。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとしています。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとしています。
さらに上記の他、当社が吸収合併新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、当該新株予約権者から新株予約権を無償で取得することが可能としています。
② 当社株主総会及び取締役会(取締役会を置いていない場合は、取締役の過半数の決定)において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割·新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することが可能としています。なお、「新株予約権の行使の条件」の規定により本新株予約権を行使することができる場合には、当該新株予約権の行使を妨げないものとしています。
③ 当社は、本新株予約権者が本新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、取締役会(取締役会を置いていない場合は株主総会)が別途定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することが可能としています。
④ 当社は、当社と新株予約権者の間の取引関係がなくなった場合には、当該新株予約権者から新株予約権を無償で取得することが可能としています。
4.新株予約権行使の条件
① 本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項·同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(e) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法(ディスカウンテッド·キャッシュ·フロー法)、類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
② 本新株予約権の行使は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から6ヶ月が経過することを条件としています。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合はこの限りではありません。
③ 上記②の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令及び当社の定款その他の社内規則上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議または決定が行われた日以降別途当社が合理的に指定する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとしています。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味します。
(a) 当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(b) 当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社または新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(c) 当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(d) 当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(e) 他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(f) 当社が事業譲渡または会社分割により当社の事業の全部または重要な一部を第三者に移転させること。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の権利行使は認めないものとしています。ただし、取締役会(取締役会を置いていない場合は取締役の過半数の決定)が認めた場合はこの限りではありません。
⑤ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各本新株予約権の一部の行使は認められないものとしています。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは不可能としています。
⑦ 新株予約権者は、上記②もしくは③の定めに加え、「新株予約権を行使することができる期間」及び以下(a)から(d)において定める期間区分に従って、本新株予約権の一部または全部を行使するものとしています。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数としています。
(a) 割当日から起算して1年を経過する日までの間は、割当てられた本新株予約権を行使できないものとする。
(b) 割当日から起算して1年経過した日から、割当日から起算して2年を経過する日までの間は、割当てられた本新株予約権個数のうち、3分の1までの本新株予約権を行使することができるものとする。
(c) 割当日から起算して2年経過した日から、割当日から起算して3年を経過する日までの間は、割当てられた本新株予約権個数のうち、3分の2までの本新株予約権を行使することができるものとする。
(d) 割当日から起算して3年経過した日以後は、割当てられた本新株予約権のすべてを行使することができるものとする。
5.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)3に準じて決定する。
6.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
7.本新株予約権は、新株予約権1個につき60円で有償発行しています。
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.株式分割(1:1,000)によるものです。
2.新株予約権の行使によるものです。
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです(減資割合20.3%)。
4.株式分割(1:20)によるものです。
(4) 【所有者別状況】
(注) 1.2025年6月30日開催の取締役会決議により、2025年7月17日付で1株につき20株の株式分割を行っています。
2.2025年7月30日開催の臨時株主総会決議により、2025年7月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。
(5) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、剰余金の利益配分につきましては、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断した上で配当を行っていくことを基本方針としています。しかしながら、当社は本書提出日現在、事業拡大過程にあり、財務体質を強化し、事業拡大に再投資するために、創業以来無配当としていました。今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針です。内部留保資金につきましては、今後の事業戦略に応じて、海外展開への投資資金や新ブランドの立ち上げまたは買収のための資金として有効に活用していく方針です。また、剰余金の配当の基準日は、期末配当は1月31日、中間配当は7月31日、その他基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めていますが、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は定めていません。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長及び長期安定的な企業価値の向上を経営の重要課題としています。
その実現のためには、株主の皆様、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、お客様にご満足していただける商品やサービスを提供し続けることが重要と考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主な機関として、取締役会、監査役会、リスク・コンプライアンス委員会、コーポレート・ガバナンス特別委員会、及び内部監査室を設置しています。
イ.取締役会
取締役会は、代表取締役 松沼礼が議長を務め、取締役 柳澤純一、取締役 鳩山玲人、社外取締役 岡本紫苑、社外取締役 デーヴィッド・マークスの5名で構成されています。取締役会は、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。具体的には、当社の経営戦略や中期的な経営方針の承認、これら計画に対する実績の進捗確認・分析の報告、規程の制改定等の内部統制に関する事項等について検討しています。
また、取締役会には、すべての監査役3名(うち社外監査役3名)が出席し取締役の業務執行の状況を監視する体制となっています。
ロ.監査役会
監査役会は、常勤監査役 川崎美香が議長を務め、非常勤監査役 弓削田博、非常勤監査役 大熊将人の3名(うち社外監査役3名)で構成されています。
監査役会は、原則として1ヶ月に1回開催される他、必要に応じて臨時に開催しています。監査役会規程に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っています。
監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、業務及び財産の状況を監査するとともに、監査法人及び内部監査部門等から報告を受ける等緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監査しています。
ハ.経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する協議・意思決定機関として設置しています。
代表取締役 松沼礼が議長を務め、取締役 柳澤純一、取締役 鳩山玲人で構成され、常勤監査役 川崎美香が陪席して意見陳述が可能となっています。
原則として2週間に1回開催し、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況の確認等を行っています。
ニ.リスク・コンプライアンス委員会
全社リスクの管理及びコンプライアンス遵守に向けた取り組みを行うための機関として、代表取締役を委員長として取締役会の決議に基づき選任された委員を構成員(委員長:代表取締役 松沼礼、委員:取締役 柳澤純一、取締役 鳩山玲人、オブザーバー:社外監査役 川崎美香)とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しています。
同委員会は四半期に1回の定期開催の他、必要に応じて臨時に開催され、事業活動に関連する潜在的なリスクの把握と予防策の立案、顕在化したコンプライアンス違反への対処方針の策定や再発防止策の立案、ならびにそれらの取締役会への上程や承認された方針・対策等の推進を主な役割としています。
ホ.内部監査室
内部監査室は、内部監査人3名で構成されており、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し、法令遵守、内部統制の実効性等を監査しています。監査結果については、取締役会及び監査役会に報告を行うとともに、監査役会及び監査法人と相互連携を深めるため、適宜情報交換を行っています。
へ.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しています。同法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けています。
ト.コーポレート・ガバナンス特別委員会
支配株主との取引の公正性を確保するため、独立役員(社外取締役2名(岡本紫苑、デーヴィッド・マークス)及び社外監査役3名(川崎美香、弓削田博、大熊将人))から構成されるコーポレート・ガバナンス特別委員会を設置しています。支配株主との取引については、取締役会から当特別委員会に対して諮問し、その答申を踏まえて取締役会において意思決定しています。
b.企業統治の体制を採用する理由
迅速かつ適切に経営判断ができるように上記のような企業統治の体制を採用しています。また、社外監査役は専門的な知識や経験に基づき、業務執行に対する十分な監査機能を担っており、コーポレート・ガバナンス特別委員会、内部監査室及びリスク・コンプライアンス委員会を設置することで、より一層の経営監視機能が果たされていると考えています。
c.当社のコーポレート・ガバナンス体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、以下のとおりです。
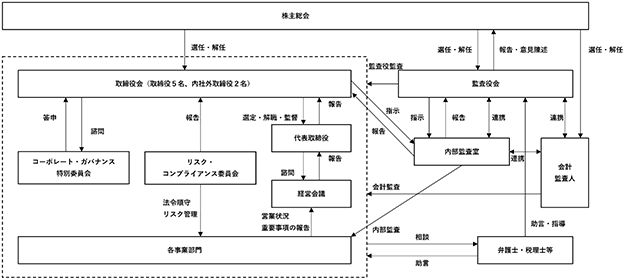
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は2025年5月22日開催の取締役会において、「会社の業務ならびに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備の方針」を基本方針の一つとして含む、「内部統制システムの基本方針」を決議しています。会社法、会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、「定款」に適合することを確保するための体制その他当社における業務の適正を確保するため、「内部統制システムの基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めます。
内容は以下になります。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、すべての活動の基本となる“MISSION”及び“VALUE”を定め、高い倫理観を持って企業活動を行う組織風土を構築するためにコンプライアンス関連規程を整備する。取締役及び従業員は、これらを職務執行の拠り所とすることで、法令及び定款ならびに社内規程等を遵守する。
ロ.リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する方針、活動計画等を定め、会社全体のコンプライアンスの推進を図る。また、コンプライアンス担当部署である法務部門を事務局として、コンプライアンス上の課題の検討等を行い、教育・研修を徹底する。
ハ.取締役会は、取締役に職務の執行状況を定期的に報告させ、取締役の法令及び定款ならびに社内規程等の遵守状況を把握する。
ニ.法令及び定款ならびに社内規程等の違反行為等に関する従業員からの通報に対応するため「内部通報規程」を定めるとともに、不正行為の早期発見を図るため、社内外に内部通報窓口を設置する。
ホ.職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、各職責の職務範囲や決裁権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。
へ.内部監査部門は、会社の法令及び定款ならびに社内規程等の遵守体制の有効性について内部監査を行い、取締役会及び監査役会に内部監査結果を報告する。内部監査を受けた部署及びその関連部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
ト.万一、法令違反等が発生した場合には、「就業規則」に則り厳正に処分するとともに、主管部署及び内部監査部門ならびにリスク・コンプライアンス委員会と相互に連携し再発防止のための対策を講ずる。
b 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「秘密情報管理規程」その他関連する規程に従い、情報種別ごとに適切な保存期間を定め保存及び管理する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査役から要請があった場合に備え、常時閲覧可能な状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規定その他体制
イ.「リスク・コンプライアンス規程」に則り、代表取締役が委員長となり、経営会議の決議に基づき選任される委員を構成員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。同委員会は、経営方針または中期的な経営戦略や経営指標の実現を阻害する要因となりうる会社全体のリスク情報を網羅的に収集し、分析・評価を行い、リスクへの対応を検討し、統括することで、損失の危険の管理を行う。
ロ.リスクマネジメントの担当部署である法務部門を事務局として、各部署のリスク管理の状況をとりまとめ、その結果を定期的にリスク・コンプライアンス委員会に報告する。リスク・コンプライアンス委員会は、報告内容に基づき改善策を審議、決定し、リスク管理態勢とその有効性の継続的改善を行う。
ハ.リスク・コンプライアンス委員会は、大規模災害等の危機発生時に適宜対策室を設置して、情報の一元管理を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる活動を行う。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規程」「職務権限規程」その他関連する規程を定めるとともに、取締役会を原則として毎月1回開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。
ロ.「会議体規程」及び「経営会議規程」により、業務執行取締役が出席し、常勤監査役が陪席する経営会議を原則として隔週で開催し、重要な業務執行の一部の決定及び利益計画の進捗状況の管理に関して、取締役会から委任を受け、機動的な意思決定を図る。
ハ.取締役会は、中期経営計画及び年度計画の策定を行い、年度計画に基づく部門ごとの業績目標や予算の設定を行うとともに、月次または四半期ごとの予実管理を含む全般的な統制活動の実施を行う。
e 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
ロ.会社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性および監査役の指示の実効性に関する事項
イ.監査役または監査役会が求めた場合には、監査役の業務を補助すべき従業員を置くものとし、当該補助すべき従業員の人事は、監査役または監査役会の意見を尊重する。
ロ.補助すべき従業員への指示は、取締役から独立して行われるものとし、当該補助すべき従業員は、監査役の指示に基づき業務を行う。
g 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や法令及び定款ならびに社内規則等に違反する恐れのある行為を発見した場合は、速やかに監査役に報告する。また、コンプライアンス上重要な内部通報があった場合は、通報状況を速やかに報告する。
ロ.当社の監査役は、内部通報制度の運用状況について四半期に一度報告を受ける。また、必要と認めた場合。直ちに運用状況について報告させることができる。
ハ.監査役は、取締役会その他の会社の重要な会議に出席し、審議事項に関して必要があるとき、または求めに応じて意見を述べることができる。
ニ.取締役会及び会社は、監査役に対し、必要に応じて、内部監査部門との情報交換や会社の監査法人から会計監査内容に関して説明を受ける機会や情報交換等を行うことができる体制を整備する。
ホ.監査役への報告を行った取締役・従業員に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.会社は、監査役または監査役会から監査役の職務の執行について生じた合理的な費用または償還の請求があった場合はすみやかに処理をする。
ロ.監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、顧問法律事務所等に専門的な助言を求め、会計監査業務については、監査法人に意見を求める等必要な連携を図る。
ハ.監査役は、監査役監査の実効性を確保するための体制を含む内部統制システムの構築・運用に関し、必要があると認めたときは、代表取締役その他関係する取締役との間で協議の機会を持つ。
i 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
イ.当社は、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たないことを基本方針とする。反社会的勢力からの不当要求に対しては、社内体制を整備し、同規程に基づき対処を行う。
ロ.反社会的勢力への対応部署を法務部門に設置し、各部署の対応に関する指導・支援を行う。緊急時における警察への通報、顧問弁護士への相談を実施する等、外部の専門機関との連携を図り、体制強化に努める。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を強化するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。また、「リスク管理規程」を定め、リスク情報を早期に把握・共有し、リスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めています。なお、リスク・コンプライアンス委員会の開催頻度については、四半期に1回もしくは必要に応じて開催しています。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めています。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨についても、定款で定めています。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元の実施を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により、剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めています。
c.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
⑩ 取締役会の活動状況
当社は最近事業年度において取締役会を原則として月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。なお、最近事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下になります。
取締役会における具体的な検討内容は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、重要な経営戦略、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等、設備投資に関する事項が主たる事項です。
⑪ 役員賠償責任保険契約等
当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料を当社が負担しています。当該保険契約等では、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。なお、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しています。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 岡本紫苑、取締役 デーヴィッド・マークスは、社外取締役です。
2.常勤監査役 川崎美香、監査役 弓削田博は、監査役 大熊将人は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2025年7月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2025年7月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
社外取締役の岡本紫苑氏は、日本及び米国の弁護士資格を有し、国内外の法務案件に従事した経験から、リスクマネジメントにおける高い専門スキルのほか、新規事業における現場経験や財務・会計に関する知見も併せて有しています。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、ESGやダイバーシティの視点における有効な助言とともに、当社の経営全般における実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のデーヴィッド・マークス氏は日本のファッションや音楽などについて、ライターとして多彩な執筆の実績があるほか、著名な雑誌での連載を持っており、カルチャー・ライフスタイル及びファッション業界における豊富な知識と経験を有しています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、ESGやダイバーシティの視点において、多様な提言をいただけるものと考えており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、客観的かつグローバルな視点で、当社の経営に客観的な立場から適切な発言を行っていただけることが期待できると判断したため、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役の川崎美香氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の弓削田博氏は、弁護士及び弁理士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大熊将人氏は、新規事業開発及び投資事業の分野において幅広い事業経験を有しており、当社の次世代事業の開発やグローバル展開に関する業務執行に対して客観的かつ独立した視点で経営全般の監督と有効な助言が期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考に、当社の定めた独立役員の独立性判断基準に沿って選任しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っています。
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めています。また、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しています。
社外監査役は内部監査人からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査人及び監査法人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しています。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2025年4月25日の定時株主総会において、監査役会設置会社へと移行しています。当社の監査役会は、独立性を確保した監査役3名で構成され、その全員が社外監査役であり、公認会計士・弁護士の資格を有している監査役や、新規事業開発及び投資事業の分野において幅広い事業経験を有している監査役などそれぞれが、専門的な見地から監査を行っています(なお、監査役 川崎美香は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています)。また、原則月1回監査役会を開催し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めており、必要に応じて臨時の監査役会を開催しています。
なお、2025年1月期においては監査役会の前身となる監査役協議会を設置しており、最近事業年度の定時株主総会後(2024年4月26日以降)における監査役協議会の開催状況は下記のとおりです。
監査役監査においては、当社の健全で持続的な成長の確保と社会的信頼の向上に応えるコーポレート・ガバナンスを確立するため、公正不偏な姿勢を保持し、役員及び従業員との意思疎通ならびに内部監査室・会計監査人ならびに社外取締役等との緊密な連携を図り、もって取締役の職務執行の適法性の観点から監査を行うと共に、経営管理体制の向上に資する監査を実施しています。具体的な検討事項としては、取締役会等の意思決定や取締役会への報告状況及び取締役会の監督機能の履行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況に係る監査、法令遵守状況の監査及び協業取引、利益相反取引、関連当事者取引の監査等を実施しています。
各監査役は、取締役会その他重要会議に出席する他、業務執行取締役との会合や意見交換を通じて経営に対する監査を行っています。また、各監査役ならびに内部監査担当者は、監査計画の策定・実施・監査結果について定期的に情報共有を行い、業務の適法性及び内部統制(財務報告の適正性を含む)の整備・運用状況について連携して監査を行っています。監査法人とも定期的な面談を実施し、情報共有・意見交換を行い、監査の質の向上を図っています。
常勤監査役の活動としては、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っています。加えて、監査法人及び内部監査担当と密に連携を図ることで、深度ある監査の実施に努めています。なお、これらの結果については、適宜監査役会で報告し、監査役間で情報を共有しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会及び監査役会へのデュアルレポートライン制を採っており、本書提出日現在3名の体制で構成されています。取締役会の承認を得た年次内部監査計画に基づいて、被監査部門に対して書面による事前調査と関係資料の査閲を経て、ヒアリング等を実施し網羅的に内部監査を実施しています。
監査の結果は、期中においては、監査終了後、被監査部門の担当取締役に報告しています。また、報告後の改善事項の指示、フォローアップをした上で改善報告書を被監査部門の担当取締役に提出しています。
なお、最終的には、年間の監査計画に基づく監査終了後に、取締役会にて監査結果報告をしています。
監査役会と会計監査人を含めた四半期ごとの決算後の意見交換会において、情報交換・意見交換を行っており、監査役会、会計監査人とも相互の連携を密にして監査の実効性向上に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 古谷大二郎
指定有限責任社員・業務執行社員 能勢直子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他16名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性ならびに監査報酬等を総合的に勘案し選定することとしています。
有限責任監査法人トーマツを監査法人として選定した理由は、監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためです。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人による計画説明及び結果報告等を通じて、独立性と専門性の有無を確認しています。その結果、監査法人の独立性、専門性ともに問題ないものと判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
現時点では、当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針等を定めていません。財務・経理部において稟議申請を行い、取締役会または経営会議にて承認しています。重要契約のため、通常は取締役会での決議事項となりますが、2024年1月期においては前期と金額が同額であること、契約の更新であることから経営会議での決議事項となっています。なお、2025年1月期においては金額は増加したものの毎期更新される契約という点を考慮し、経営会議において決議しています。
今後については、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、監査役会の同意を得た上で決定する方針です。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、関係部署からの報告をもとに会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠、また他社の情報などを勘案し審議した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、同意しています。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬限度額に関して、取締役報酬につきましては、2023年4月25日開催の定時株主総会において、年額400,000千円(決議時点での取締役の員数は6名)、監査役報酬につきましては、2024年4月26日開催の定時株主総会において、年額60,000千円(決議時点での監査役の員数は2名)とする旨決議しています。
ロ.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
1)役員報酬制度に対する基本的な考え方
役員報酬制度は当社が目指すミッション・ビジョンの実現に向けて適切な動機付けの構造を組織に組み込むための重要な制度と考えています。
中長期的・持続的な成長に向けて経営陣に適切なリスクテイクを促しつつ、コーポレート・ガバナンスを担保し経営責任が的確に報酬に反映される制度を目指しています。
2)報酬構成
当社役員(社外取締役・監査役を除く)の報酬構成は以下の通りです。
固定報酬を60%前後とし、業績連動報酬部分が40%前後となっています。業績連動報酬部分はSTI(Short Term Incentive)20%前後、LTI(Long Term Incentive)20%前後とし、短期的成果・中長期的成果を適切に反映する構成を目指しています。
業績連動報酬部分40%前後の比率設定にあたっては、市場平均や当社がベンチマークとする企業群の比率などを参考に定めています。
なお、社外取締役・監査役についてはその役割に鑑みて全て固定報酬としています。
*上場前の段階では株式報酬の代わりに現金報酬(固定額)としています。上場後、準備が整った段階で株式報酬への切り替えを予定しています。
3)業績評価指標の考え方
3-a.STI
STIは以下の指標を用いて係数を算出し、当該係数とSTI標準額を乗じて算出します。
係数の算出にあたって売上高と営業利益双方の目標達成率を勘案する理由は、当社がバランスの取れた成長を重視しており、片方に偏った施策に陥ることのないことを企図しています。
STI標準額(固定)×係数
係数=売上高目標達成率*×営業利益目標達成率*
*目標達成率=当期実績÷事業計画上の売上高または営業利益
3-b.LTI
LTIは株式報酬であるため、支給後の中長期的な株式価値の上昇が中長期的かつ客観的に報酬に反映されると考えています。
4)報酬水準
報酬水準の設定にあたっては、市場全体、ベンチマーク企業群との比較検討の他、採用における競争力を踏まえて設定しています。
5)報酬額の決定プロセス
当社の役員報酬は、役員報酬規程及び細則に定められたルールに則り算定されます。報酬の決定は代表取締役への一任決議ですが、原則的に裁量の余地はなく、実績としても調整されずにルール通りの計算で支給されています。
上記の役員報酬関連の制定にあたっては客観性を担保すべく外部コンサルタント会社を起用して助言を受け、取締役会において決議しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。