第二部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首から適用しており、第6期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第3期から第7期については、マーケティング等の先行投資や今後の成長に向けた人員増加に伴う給料手当の負担等により、経常損失及び当期純損失を計上しております。また、同様の理由により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社が存在しないため記載しておりません。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であり、期
中平均株価が把握できないため、また当期純損失であるため、記載しておりません。
6.第3期から第7期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
7.株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
8.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数を〔 〕外数で記載しております。
9.主要な経営指標等のうち、第6期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第5期以前キャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。
10.第6期及び第7期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、みおぎ監査法人により監査を受けております。なお、第3期、第4期及び第5期については、「会社計算規則」(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
10.2024年9月17日開催の取締役会において、A種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年10月2日付で自己株式として取得し、対価として定款に定められた普通株式への転換請求権の比率に応じた数の普通株式をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。これにより、発行済株式総数は普通株式3,820,498株となっております。なお、2024年9月17日開催の臨時株主総会において、A種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る定款の定めを廃止しております。
2 【沿革】
3 【事業の内容】
当社は、「法とすべての活動の垣根をなくす」をパーパスとし、法律とIT技術を融合した「リーガルテック」により、法務と他の業務・活動を統合し、企業や個人がより創造的かつ効果的に活動できる社会を実現することを目指しております。
当社は、リーガルテック事業として、主に法務部門や法律事務所向けに法務業務のDX(注1)を推進する「LegalTech SaaS事業」及び社内に法務機能が無いようなスタートアップ企業や中小企業でも簡単に登記手続きが行える「登記事業」の2つのサービス群を主要なサービス群として提供しております。
なお、当社はリーガルテック事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(1) LegalTech SaaS事業
当社は、LegalTech SaaS事業として、全社を支える法務OS「OLGA」を、SaaS型のクラウドサービスとして自社開発し、提供しております。「OLGA」は、「AI(注2)法務アシスタント」「法務データ基盤」「AI契約レビュー」「契約管理」の4つのモジュールから構成されており、法務部門の業務におけるデータベース構築・ナレッジ活用・リスクの可視化・円滑な事業部門側とのコミュニケーションを通じて、組織全体の工数削減と業務クオリティ向上を最大限に支援します。
なお、「OLGA」の各モジュールは、個別に導入することも可能であり、顧客企業のニーズや既存業務に応じたソリューションを提供することが可能です。
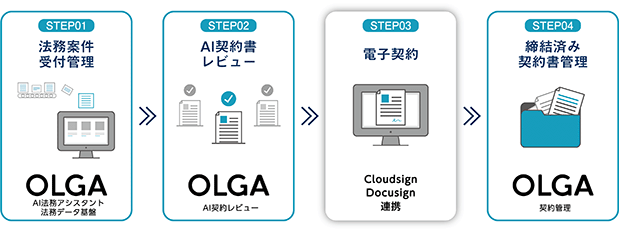
「OLGA」の各モジュールについて、ご説明いたします。
①AI法務アシスタントモジュール/法務データ基盤モジュール
法務部門では、契約書のチェックや新規事業のリスク調査等、日々様々な案件依頼が発生します。従来は、依頼部門から電話・メール又は汎用的なワークフローツールにより案件を受付し、それらの案件の進捗状況をExcelに手入力して管理することが一般的です。また、依頼された案件に関するやり取りは電話やメール、ビジネスチャットツール等様々な手段で行うことが多く、やり取りの内容が散在している、又は担当者個人の管理にとどまり、組織内に共有がされていないことも多くあります。そのため、法務部門内で担当している案件の進捗管理ができず納期遅延に気づかない状況の発生や、過去のナレッジが蓄積されていないことから業務の非効率化および担当者の退職・異動による案件のブラックボックス化が生じるリスクがあります。法務部門の業務において、過去の規範や法律の解釈、交渉した経緯等の過去のナレッジは非常に重要であり、これらを体系的に集約するナレッジマネジメントは非常に高い関心を持たれております。
法務データ基盤モジュールでは、メールやビジネスチャットツールと連携することにより、法務案件を一元的に集約し、案件の進捗管理やタスク管理、メンバーの工数管理等を実現します。また、事業部門とのコミュニケーションも、すべてモジュール内で行うことができるため、案件に関わるあらゆる法務の情報が集約され、これまでは蓄積・管理されずに散逸していた情報についても容易に検索・抽出・活用することができます。
また、データ分析ダッシュボード機能により、月別の依頼案件数や依頼部署ごとの案件内容の傾向、メンバー毎の対応件数等を把握することができ、業務効率化施策の検討や、法務部門の人員計画や育成計画の立案等にも活用することができると考えております。
AI法務アシスタントモジュールは、法務データ基盤モジュールで一元管理されたこれらのデータを活用して、定型的な相談内容を自動データベース化して事業部門に回答してくれたり、依頼案件に対して過去に対応したことのある案件の中から類似の案件を検索・提案する等の機能をチャットボット形式で提供します。法務部門だけでなく、事業部門も利用することができるため、法務部門の対応工数の削減に加えて、事業部門では定型的な相談であれば瞬時に解決するため事業を進めるスピードの促進を図ることが可能と考えております。
②AI契約レビューモジュール
企業が取引を開始する場合、基本的にはすべての取引において契約書を作成する必要があります。契約書に不備がある場合、取引先等から過大な損害賠償を受けるリスクや、事業に必要な知的財産権が喪失してしまうといった、事業継続上、非常に重大なリスクが生じることがあります。
これらのリスクを防ぐため、法務部門は事前に契約審査という業務によりチェックを行い、取引先との交渉に応じて都度契約書の確認や修正を行います。法務担当者は、取引開始までのスケジュールに合わせるために、短いリードタイムでの確認が必要であり、かつ様々な部門からの依頼に並行して多くの契約書の確認を行う必要がある一方で、昨今では様々な先進技術やビジネスモデルの出現に伴う各種法規制への対応が必要になり、法務担当者の契約審査に求められるレベルは年々高度化しております。
AI契約レビューモジュールでは、以下の機能を提供することにより、従来はほとんど人力でチェックをしていた膨大な量の契約書の審査業務において、業務品質の向上・業務効率化を実現することができると考えております。
特に、「OLGA」のAI契約レビューモジュールの特徴としては、論点検知機能について利用企業独自の基準にカスタマイズ可能な点にあります。
論点検知機能は、予め「OLGA」内に設定された契約書のひな型とレビュー対象の契約書とを、当社が独自に開発したAIが照らし合わせたうえで条文の抜け漏れやリスクとなる単語を検知します。この予め設定された契約書のひな型を顧客企業が独自にカスタマイズし、顧客企業のルールやマニュアルに応じた条文や単語のチェックを行うことができます。大手企業等、法務部門がある程度成熟してくると、自社の業種やカルチャー、過去のトラブル事案等を参考に、独自のルールやマニュアルが形成されていることが多く、カスタマイズのニーズが非常に強いため、これらの要望に応えるための「自社の基準にカスタマイズした契約審査」の機能を強化してまいりました。
③契約管理モジュール
多くの企業では契約書は締結するものの、適切に管理が行われておらず、契約期間が必要以上に更新されることで経費が過大にかかったり、過去の契約書の探索に非常に時間を要して業務の生産性が低下してしまうといった事態が生じております。「OLGA」の契約管理モジュールでは、契約書のデータをアップロードするだけで、AIが自動で以下の項目を抜き出し、管理台帳を自動で作成・管理することが容易になるとともに、契約期限のアラートを自動で通知することにより、更新や終了の漏れのリスクを低減します。
(自動抜き出し項目の例)
・取引先名
・契約締結日
・契約開始日
・契約終了日
・契約終了の条件
・自動更新の有無
・更新拒絶期限日
・更新後の契約期間
なお、LegalTech SaaS事業の収益モデルは、サブスクリプション型の収益であり、利用アカウント数等に応じた月額利用料と、導入時の初期導入費用等のスポット料金を受領しております。
(2) 登記事業
当社は登記事業のサービス群として、商業登記における変更申請の書類を簡単に作成することができる「GVA法人登記」、法人の履歴事項全部証明書等を簡単に請求できる「GVA登記簿取得」を提供しております。
①GVA法人登記
商業登記とは、商法や会社法等の法律で定められた、会社において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的等)を、商業登記簿に記載することで一般に公示する制度です。記載された事項を変更する場合、必ず変更申請の手続きを行う必要があります。
これらの変更申請のための書類は、会社の種類や機関設計等により、提出する書類や内容が変わるため、専門家以外が自力で作成する場合非常にミスが多くなってしまいます。そのため、司法書士に依頼するケースも多いですが、その場合は費用や期間がかかる、自分に合った司法書士を探すのに手間がかかると言った課題があります。
GVA法人登記では、指定したフォームに必要事項を入力すれば、変更登記に必要な書類が自動作成され、自力で作成するよりも「簡単・確実に」、司法書士に依頼するよりも「スムーズに・安く」手続きを行うことができます。
特徴としては、法務局から連携される登記情報PDFから変更前の情報を自動で反映する「登記情報自動反映機能」と、書類を製本して法務局送付用のレターパックや収入印紙等を購入者にお届けする「かんたん郵送パック」のオプションを提供することにより、より簡単・確実に変更登記の申請が行えることです。特に「登記情報自動反映機能」は、従来であれば申請書類に現在登記されている会社名や住所等の基本情報を正確に手入力する必要があるところを、この機能を利用するとシステム内で現在の登記情報を取得し、基本情報が書類作成画面に自動反映されるため、申請書類作成上の手間や入力ミスを減らすことができます。
累計で約20,000社の企業に利用いただいておりますが、政府の統計によると、年間約100万件の変更登記申請が行われているため、認知を拡大しよりシェアを拡大するように努めてまいります。
なお、利用顧客のアンケート(注3)では、約9割の顧客が「必ず利用する」又は「たぶん利用する」と回答しており、顧客満足度の高いサービスと考えております。また、同アンケート調査により、登記申請の際に、申請書等の不備で訂正等が発生する比率(補正率)がGVA法人登記経由の場合一部の手続きにおいて9.9%の結果で、法務省の目標値(注4)である20.4%を大きく下回る結果が出ており、行政手続きの効率化へ貢献しております。

②GVA登記簿取得
履歴事項全部証明書等を法務局に請求し入手する場合、対応時間が限定されていること、支払方法が限定されていること等から、取得に制限があり、ニーズに適さない場合があります。また、法務省よりオンラインで取得できるWebサービスも公開されておりますが、使いづらいUI/UX(注5)や事前の手続きがやや煩雑なサービスになっております。
GVA登記簿取得では、24時間365日、Webサイト上から交付請求ができ、またシンプルなUI/UXによりわかりやすいWebサービスで、最低限の情報入力とクレジットカードでの支払いにより、最短1分程度で請求ができます。
なお、登記事業の収益モデルは、トランザクション型の収益が中心であり、利用者による手続きの都度、サービス利用の料金および書類の印刷、製本等を代行するオプション料金を受領しております。
(注)1.DX(Digital transformation、デジタル変革)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することです。
2.AI(Artificial Intelligence、人工知能)とは、コンピュータを用いて「認識、言語の理解、課題解決」などの知能行動を実行する技術です。
3.GVA法人登記を2022年10月1日から2023年9月30日までに利用した顧客への当社独自アンケート調査であり、有効回答数は303社。
4.法務省ホームページ「規制改革推進会議行政手続き部会取りまとめに基づく基本計画について」より引用。
5.UIはUser Interfaceの略称で、デザインやフォント、外観等ユーザーの視覚に触れる全ての情報のことを指し、UXはUser Experienceの略称で、ユーザーが製品・サービスを利用する一連の行動の中で得た経験、感じたことを指します。
[事業系統図]
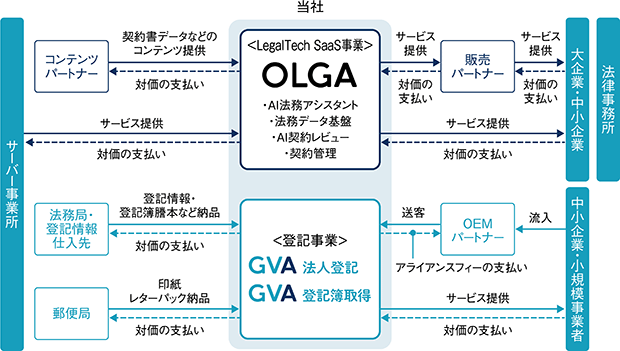
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
(注) 1.臨時雇用者数(契約社員及びアルバイト)は、最近1年間の平均雇用人員を〔 〕外数で記載しております。
2.リーガルテック事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。